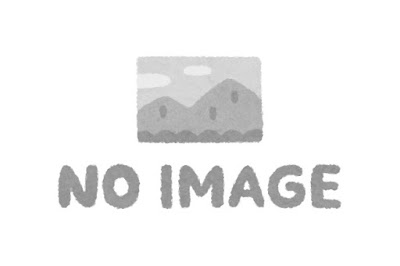こんにちは
皆さんはBlenderのバージョンは何を使っていますか???
昔からいろんなアドオンを入れてる人や、新しいUIになれない人は2.79だったり、
最近インストールした人やこまめに更新してる人は今年の8月19日にリリースされた2.83.5でしょうか?
私はどちらかというと前者で、2.79をずっと愛用していました。
ご存じのとおり、Blenderは去年の7月にVer2.8が正式にリリースされ、初心者にとって非常に使いやすいUIに変わりました。

しかし、私は新しいUIに慣れることすら怠り、1年近くずっと2.79にしがみついていました。
そんな私に先日、後輩にBlenderに使い方について教える機会があり、
さすがに1年前のリリースかつ、一般的に使いにくいと言われている2.79をインストールさせるわけにもいかずに
名残り惜しさを感じつつも、最新のBlenderを教えるために最新の2.83.5をインストールしました。
その時に最初に表示される設定に分かりにくいところがあったので、今回はそれについて解説していきます。
起動直後の設定
Blenderを初回に起動するとまず、最低限の設定ができるウィンドウが表示されます。

(うっかりウインドウを消してしまったり、初回起動後にそのままBlenderを閉じてしまった人は後述の『設定しなおしたいときは』を読んでください)
項目が5つあり、上から順番に
Language – 言語
Shortcuts – ショートカットキーと対応する操作の組み合わせ
Select With – 左右どっちのクリックで頂点やオブジェクトを選択するか
Spacebar – スペースバーを押したときの挙動
Theme – 画面テーマ です。
Languageは日本語もあるのでそれを選ぶことをお勧めします。
ShortcutsはBlender・Blender27X・Industry Comoatibleの三種類から選べます。
Blenderは現行のショートカット、
Blender27Xはバージョン2.70(2014年3月) ~ 2.79(2017年9月)の時のデフォルトのショートカット、
Industry Comoatibleは他の3Dソフト(Mayaなど)のショートカットを含めた業界互換となっています。
Blenderの過去バージョンを使っていた人は2.7Xに、
Mayaなどのソフトを使っていた人はIndustry Comoatibleに、
他の人は特に理由がないならBlenderでいいでしょう。
あくまでここでは一括で設定できるというだけなので、のちに一部のショートカットを変更することも可能です。
Select Withは左右の使いやすい方を選ぶといいでしょう。
これも過去バージョンに慣れている人以外はデフォルトの左クリックのままでいいと思います。
(今は左クリックがデフォルトですが2.79以前は右クリックがデフォルトでした)
Spacebarはアニメーション機能を使う方はPlayのままでいいと思います。
Blenderでモデリングをメインにしたいという人はToolに選択するのも選択肢の一つだと思いますが、
スペースキーを押して出てくるツールは、全て画面の左にあるものです。

そのため、私はスペースバーには使いたい機能を調べるためにSearchを入れています。
Themeは画面の配色を決めるためのものです。
明るめのものやデフォルトの暗い画面や他の3Dソフトのような色合いを選択できます。
ここもこだわりがないのならデフォルトでいいと思います。
設定しなおしたいときは

詳細な設定は画面右上の 編集 → プリファレンス から行うことができます。
初回起動時の5つの項目の設定を飛ばしてしまったり、もう一度行いたいときはそれぞれ以下のような方法で設定しなおすことができます。
Language – インターフェイス(Interface) → 翻訳(Translation)から使いたい言語を選択し、ツールチップとインターフェースのチェックボックスにチェックを入れる
Shortcuts – キーマップ(Keymap)からウインドウ上部のプルダウンから選択
Select With – キーマップ(Keymap) → プリファレンス(Preferences)内のSelect With Mouse Button
Spacebar – キーマップ(Keymap) → プリファレンス(Preferences)内のSpacebar Action
Theme – テーマ(Themes) ウィンドウ上部のプルダウンから選択
他のソフトやアドオンとの互換性のために
ここまでの設定が完了したならばBlenderは問題なく使うことができます。
しかし、海外製のアドオンを導入したり、他のソフトと合わせて使う場合は変えておきたい設定があります。
それは言語についての設定です。
具体的には Language – インターフェイス(Interface) → 翻訳(Translation)の中にある 『新規データ』のチェックボックスです。
この設定で何が変わるのかといいますと、新たに生成したオブジェクトの名前が変わります。
例えば平面を追加するとき、このチェックボックスを入れていると生成されるオブジェクトの名前が『平面』に
チェックを入れていないと『Plane』になります。
「それだけ?」と感じる方もいるかもしれませんが、これが結構重要な設定です。
日本語や全角英数字は2バイト文字という半角英数字などの1バイト文字の256倍のデータ量を持つ字で、英語圏では基本的に使われていません。
そのため、海外の1バイト文字だけを使うことを前提としているプログラムやソフトなどに、2バイト文字が含まれたデータを読み込ませるとエラーが起きる場合があります。
よってチェックを外しておくことをお勧めします。
もちろん、これはファイル名やディレクトリについても同じことがいえます。
ファイルを保存するときはなるべく1バイト文字を使い、ドライブの直下などの日本語のファイル名が入らない場所に保存しましょう。
まとめ
ここまでの設定を全て適用すると以下のようになると思います。
(テーマは割愛)


インストールした後に知ったことなのですが、Blender 2.83は2年間近くサポートを続ける長期リリースになるそうで、
2.9がリリースされた後も2.9への重要な修正は、定期的にBlender 2.83にも移植されるようです。
もし、あなたがまだ2.79を使っているのならば2.83をインストールしてみてはいかがでしょうか?
2.79に入れたアドオンを消したくないという方は、インストールフォルダを変えることで過去バージョンとの共存も可能です。

今回の記事では最初の設定について、簡潔に説明させていただきましたが、
後半の記事では初回起動時のウィンドウでは設定できなかった項目のおススメの設定について書いていきます。
そちらもよろしくお願いします。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]後半の記事はこちら[/st-minihukidashi]
[st-card myclass=”” id=”1371″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]
[st-mcbutton url=”https://media-lab.pro/3yvk” title=”GyroEyeに関するお問合せはこちら” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#993399″ bgcolor_top=”#cc3399″ bordercolor=”#993399″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontweight=”bold” fontsize=”120″ width=”90″ fontawesome_after=”fa-chevron-right” shadow=”#cc3399″ ref=”on” mcbox_bg=”#ffffcc” mcbox_color=”” mcbox_title=”AR, VR. XR の活用やMicrosoft Holo Lensを活用した建築業向けソリューション”]※株式会社インフォマティクスのGyroEye公式サイトへ[/st-mcbutton]
久方ぶりです。
前回の記事に引き続きおススメの設定について紹介していきます。
前半ではインターフェースなどの設定が主でしたが、今回は操作性の設定がメインになります。
[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#f44336″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″ radius=”” position=”” myclass=”” add_boxstyle=””]前半の記事はこちら[/st-minihukidashi]
[st-card myclass=”” id=”1308″ label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on” type=””]
選択部分を中心に回転
この項目は 視点の操作 → 周回とパン の中にあります。
初期状態ではチェックボックスにチェックは入っていません。
Blenderではホイールをクリックしたままドラッグすることで視点を回すことができるのですが、この項目はその中心を決めるための項目です。
チェックしていない場合、選択物を周りから見たい場合でも選択物が動き、画面から飛び出してしまうことがあります。


Blenderを使って物を作るときには、様々な角度から形を確認することが必要になると思います。
スムーズに選択物の形を確認するためにチェックしておくことをお勧めします。
自動パース
この項目も 視点の操作 → 周回とパン の中、『選択部分を中心に回転』のすぐ下にあります。
デフォルトではチェックが入っている状態にあります。
Blenderには並行投影と透視投影の2種類の投影方法があります。
簡単にいうと並行投影は消失点が無い造形物の形を正確に映す投影方法で、
透視投影は現実のものの見え方に近く、消失点が存在するパースが入った状態で造形物を見ることができる投影方法です。
実際にモデリングするときはこの2つの投影方法を切り替えながら形を整えていくのですが、
このチェックボックスが入っているとテンキーのショートカットによる視点操作を使って視点を切り替えた後にホイールドラッグによって視点を回そうとすると必ず透視投影に戻ってしまいます。
また、透視投影でテンキーのショートカットによる視点操作を行うと強制的に並行投影になってしまい、透視投影の状態でのフロント視点・サイド視点・トップ視点ができないといったことも起こります。
平行投影と透視投影の切り替えはテンキーの5を一回押すだけでできるので、各投影方法の使い方を知っている方はチェックボックスをはずしておくことをお勧めします。
マウス位置でズーム
この項目は 視点の操作 → ズーム の中にあります。
デフォルトではチェックが入っていません。
この項目はマウスのホイールによるズームをするときに、画面のどの位置にズームするかを決めるためのものです。
デフォルトの状態だと画面のどこにカーソルを置いてズームしても、画面の中央に寄ってしまい、
ズームした後に『Shift + ホイールドラッグ』(角度を変えずに視点をスライド移動)をする手間が増えてしまいます。
このチェックボックスにチェックを入れると、ズームアウト → 対象にカーソルを重ねてズーム をすることでキーボードを使わずに画面の中心に映したいオブジェクトや頂点を変えることができます。


操作をスムーズに行うため、チェックしておくことをお勧めします。
テンキーを模倣
この設定は 入力 → キーボード の一番上にあります。
テンキーによる視点変更とはテンキーを押すことでできる以下の操作のことです。
0キー – カメラ視点
1キー – フロント視点
2キー – 下方向に15°回転
3キー – 右サイド視点
4キー – 左方向に15°回転
5キー – 透視投影 ・ 平行投影の切り替え
6キー – 右方向に15°回転
7キー – トップ視点
8キー – 上方向に15°回転
9キー – 反転

キャラクターを絵からモデリングするときには下絵と3Dを合わせるため、このフロント視点やサイド視点は欠かせないものでしょう。
ですが、一部のノートパソコンなどはテンキーがついていないことがあります。
その場合、テンキーの視点変更のショートカットをキーボード上部の数字キーに割り振るための項目がこの設定です。
しかし、良いことばかりではなく、この設定にチェックを入れることで元から数字キーにあった
(編集モード時) 1 – 頂点選択モード ・ 2 – 辺選択モード ・ 3 – 面選択モード
(オブジェクトモード時) 1 ~ 0 コレクションの表示・非表示
のショートカットが上書きされて使えなくなってしまいます。
しかし、これらの上書きされてしまう操作は画面上のアイコンをクリックすることからも行うことができるので問題ありません。
テンキーの視点変更も一部の方向は Altキー + ホイールドラッグ などの操作で代替可能ですが、
テンキー 2・4・6・8 の 『視点を15°回転』 は代替できる操作がないので、
自論としてはテンキーがない場合はチェックを入れて、数字キーにテンキーの操作を割り振ったほうがいいと思います。
テンキーがある場合は同じショートカットが2つに増えるだけなので、チェックを入れないほうがいいです。
アンドゥ回数
この項目は システム → メモリーと制限 の中にあります。
このアンドゥ回数とは 『Ctrl + Shift』(1つ前に戻る) を行える回数のことです。
この数字を増やすと作業のやり直しが効く範囲が広がるのですが、
増やせば増やすほどメモリの消費も増えます。
こまめな保存ができている人には必要はないのですが、
ちょっとしたミスを見つけてしまい、戻りたいときにこのアンドゥ回数が足りずに泣く泣く前に保存したファイルからやり直す……といった経験をしてから私は80に設定しています。
また、2.8からマテリアル等の変更もアンドゥできるようになったので、2.79でアンドゥ回数が十分でも2.8で足りなくなることもあると思います。
メモリに余裕のある方は増やしておくことをお勧めします。
まとめ
今までの設定を全て適用すると以下のようになります。(テンキーがない場合の設定)



もちろん、この設定は私が個人的にいいと思った設定なので、人によって使いやすい設定というのは違うと思います。
その最適な設定を探す手助けにこの記事がなれば幸いです。
では、快適なBlenderライフを!
[st-mcbutton url=”https://media-lab.pro/3yvk” title=”GyroEyeに関するお問合せはこちら” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#993399″ bgcolor_top=”#cc3399″ bordercolor=”#993399″ borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontweight=”bold” fontsize=”120″ width=”90″ fontawesome_after=”fa-chevron-right” shadow=”#cc3399″ ref=”on” mcbox_bg=”#ffffcc” mcbox_color=”” mcbox_title=”AR, VR. XR の活用やMicrosoft Holo Lensを活用した建築業向けソリューション”]※株式会社インフォマティクスのGyroEye公式サイトへ[/st-mcbutton]